危機管理マニュアルにあれもこれもと内容を詰め込んでしまうと、いざという時に情報が多すぎて使いにくいマニュアルになってしまいます。必要な内容のみを記載して、多くてもA4で10枚程度にまとめましょう。

「危機管理(ききかんり)」とは
企業や組織が予期しない重大な問題や災害、事故などの「危機」に直面した際に、それに対処するための計画や手段、行動を準備・実施するプロセスを指します。目的は、危機が発生した場合に被害を最小限に抑え、組織の存続や社会的信用を守ることです。
危機管理には以下のような要素があります
・予防策(リスク管理): 危機が発生する前にリスクを特定し、予防措置を講じる。
・発生時の対応: 危機が発生した際に迅速に対応できるような体制を整備する。
・回復策(復旧計画): 危機後に業務や機能を元の状態に戻すための計画を作成する。
危機管理は、自然災害、テロ、情報漏洩、企業の経営危機など、さまざまな状況に対応するために重要な役割を果たします。
1.目的・基本方針

どのような目的で危機管理マニュアルが作成されたのかを記載します。例えば、社員の安全確保や二次被害の防止、被害の最小化など、具体的に明記しておくとよいでしょう。
危機管理に対する基本方針についても明確にしましょう。例えば、「リスクマネジメントは本マニュアルに基づいて実行する」「全社員は、コンプライアンスの精神に則り、各種法令や規則などを遵守しつつ行動する」「クライシス発生時は、全社員が身の安全を確保しながら対応する」などの指針です。
2.危機レベルの設定および被害予測

対応する内容や責任者が変わってくるため、「危機レベル」の設定をしておく必要があります。発生する事案による被害規模の予測や被害額を算出することで区分できます。被害額の正確な算出は難しいですが、例えば製品に関する事故が発生した場合、
- 製品の自主回収
- 工場のライン停止
- 取引の停止
- レピュテーション低下
などのシナリオに基づき、大まかに算出しておくとよいでしょう。危機管理マニュアルを社内で共有するときは、規模の大きさに応じて数字で示したり、図表などにして色分けしたりするとわかりやすいです。
3.危機発生時の取り組み

危機が発生した直後は、迅速な対応が重要です。初動で迷わないために、具体策とその流れをマニュアルに記載するようにしましょう。以下の内容を危機管理マニュアルに盛り込むと、取り組むべき行動が明確になりやすいです。
- 危機発生直後の行動
- 現状把握のために確認すべき項目
- 対策本部の運営要領
- 対策本部の各役職者と責任権限
- 対策本部の設置場所と必要備品について
- 情報管理・社内通達・エスカレーションの方法
- 緊急時のプレスリリース・記者会見のワークフロー
- 対策本部会議の議事録テンプレート
- 危機レベル別の経過時間ごとに行うべき業務
- 危機発生時の広報指針
- 日報などで行動履歴を記録すること
4.復旧への取り組み
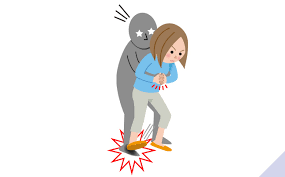
リスクが顕在化する前の状態に復旧させる取り組みが必要となります。リスクが顕在化した状態とは、災害やシステム障害、事故などの危機の発生です。業務復旧のために危機管理マニュアルへ盛り込むべき取り組みは、以下の通りです。
- 通信手段の復旧
- オフィス機能の回復
- 救援備品の調達と配送
- 業務復旧に必要な人数の把握と補給体制の確立
- 出社可能な社員の把握と勤怠管理
- 被災者への援助(居宅や手当など)
- 被害額の算出と運転資金の確保
5.危機発生時の業務指示項目

危機発生時においても企業を存続させるためには、最低限維持すべき業務や、取引先・顧客に満足してもらうための対応が求められます。維持すべき業務と事業活動レベルを各組織で定めておくようにしましょう。各組織の責任者がメンバーに対し明確な指示ができるよう、あらかじめ危機管理マニュアルの項目を洗い出すことが大切です。
6.緊急連絡網
危機のレベルや内容ごとの社内責任者や、株主や取引先、業界団体などの社外ステークホルダーの連絡先を一覧化することで、連絡漏れを防ぐことができます。
危機管理がない、または不十分な企業にはいくつかの共通する特徴があります。これらの企業は、予期しない問題が発生した際に対応が遅れたり、対応が不十分だったりするため、リスクを適切に管理できません。
リスク管理の意識が低い
危機管理体制を整備することの重要性を認識していない企業では、リスクを特定したり、評価したりすることがほとんどありません。このため、問題が発生しても事前に予防策を講じていないことが多いです。
危機発生時の対応マニュアルがない

危機管理のための明確な手順やマニュアルが整備されていない企業では、緊急時に誰がどのような行動を取るべきかが不明確です。その結果、危機発生後に対応が混乱したり、遅れたりすることが多くなります。
コミュニケーションの不足
危機発生時には迅速かつ正確なコミュニケーションが求められますが、危機管理が欠けている企業では、関係者間で情報の共有がうまくいかないことがあります。これにより、状況が悪化する可能性があります。
リーダーシップの欠如

危機発生時に冷静で適切な判断を下せるリーダーが不在の場合、企業は状況を適切に管理することが難しくなります。リーダーが危機管理の経験や知識を持っていない場合、対応が後手に回ることが多いです。
トレーニングや訓練が不足している
危機管理のための従業員向けトレーニングやシミュレーションが行われていない企業は、実際の危機発生時に従業員が適切な行動を取れない可能性が高いです。
過信や楽観的な姿勢
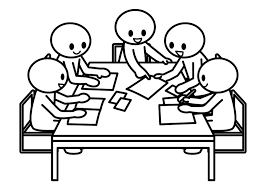
「自社は大丈夫だろう」「危機が起きることはないだろう」といった過信や楽観的な姿勢を持っている企業は、リスク管理を軽視しがちです。このような企業は、危機が現実化した際にその影響を大きく受ける可能性が高いです。
事後対応ばかりで事前対策がない
危機が発生した後に対応しようとする企業では、事前にリスクを管理する計画や体制が整っていません。そのため、問題が発生するまで準備ができておらず、対応が後手に回りやすいです。
これらの特徴を持つ企業は、危機発生時に対応が遅れたり、被害を拡大させたりすることがあります。危機管理をしっかりと行うことで、企業はより強靭に、そして持続可能に運営できるようになります。
