「米騒動」は日本近代史における重要な社会運動の一つであり、特に1918年(大正7年)に発生した全国的な騒動を指します。

米騒動とは何か?

「米騒動」とは、1918年(大正7年)に日本全国で発生した民衆による米の高騰に対する抗議運動です。富山県の漁村から始まり、全国の都市部や農村へと瞬く間に波及しました。
その過程で
単なるデモにとどまらず、商店の襲撃、米問屋への放火、鉄道の封鎖など暴動的な様相を呈する事態へと発展しました。日本の近代史において最初の全国規模の民衆騒動とされており、後に政治体制や社会制度にも大きな影響を与える転換点となりました。
背景:なぜ「米」が問題になったのか?
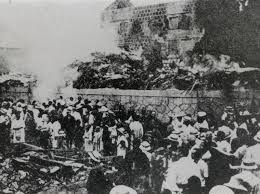
米騒動が発生した背景には、複数の社会的・経済的要因が複雑に絡み合っています。
(1) 米価の異常な高騰
第一次世界大戦(1914年~1918年)によって世界的に物価が上昇していた中、日本でも生活必需品、とりわけ「米」の価格が急騰していました。
1917年には1石(約150kg)あたり11円台だった米価が、1918年には20円を超える水準にまで跳ね上がりました。庶民にとっては死活問題です。日々の生活に欠かせない「米」が買えなくなるというのは、文字通り「飢え死に」に直結する状況でした。
(2) 国家による買い占めと輸出政策
政府は戦時経済の中で、軍への供給や満州への輸出に重点を置いており、国内での米の流通量が相対的に減少していました。商人や地主たちの中には、米を倉庫に溜め込んで価格の上昇を待つ「投機」行為も横行していました。このような動きに対し、庶民は怒りを募らせていきました。
(3) 地方と都市の格差
農村では地主による小作料の取り立てが厳しく、都市では労働者の賃金が米価に追いつかないという構造的な問題もありました。特に富山県などの漁村では、漁師の妻たちが都市に「米を買い出し」に出かける文化があり、そこで異常な価格の高さに直面したことが、運動の出発点になりました。
発端:富山の主婦たちの「嘆願」

米騒動の発端は、1918年7月23日、富山県魚津町(現在の魚津市)の漁師の妻たちが地元の米の積出を止めようとしたことに始まります。
彼女たちは「これ以上高い米を買えない」「村から米がなくなってしまう」として、米の積出港である魚津港で米の出荷を阻止しました。最初は陳情や嘆願といった平和的な手段でしたが、それが次第に力ずくの行動に変わっていき、騒動は急速に広がっていきました。
この「魚津事件」が全国に報道されると、他地域でも似たような抗議運動が頻発し始め、8月になると全国各地で暴動的な米騒動が続発します。
全国化する暴動:騒動のピーク

8月に入ると、騒動は都市部へと広がります。特に大阪・神戸・東京などでは、数万人単位の暴徒が警察署や米問屋、役所を襲撃しました。鉄道を止め、政府施設を包囲するなど、国全体を揺るがす一大騒乱へと発展していきます。
主な事例
大阪:堺市では暴徒が米屋を襲撃、米を強奪。警察との衝突が起き、多数の死傷者が出た。
神戸:港での米の積出阻止、米商人の家に火を放つ事件も発生。
東京:山谷地区などで下層労働者によるデモが発生。治安維持が困難に。
これに対して政府は、軍隊を動員し、非常事態宣言的な対応を取りましたが、それでも沈静化には時間を要しました。最終的には、全国で約70万人が参加し、25府県で騒動が発生。約25,000人が検挙され、死者も複数出たとされています。
騒動の収束と政治的影響

米騒動の影響は非常に大きく、時の寺内正毅内閣は総辞職に追い込まれました。民衆の力によって政権が崩壊するというのは、日本では初めての出来事です。
後を継いだのは原敬内閣。原敬は立憲政友会を率い、日本で初めて本格的な政党内閣を組織した人物であり、「平民宰相」とも呼ばれました。これは、日本政治における民主化の第一歩とも言える転機でした。
米騒動のその後:いつまで続いたのか?

騒動自体は、1918年の秋頃には収束しましたが、民衆の怒りが消えたわけではありません。米価の高騰や生活不安はその後も続き、1920年代には関東大震災(1923年)や世界恐慌(1929年)といったさらなる社会的混乱へとつながっていきます。
また、政府は米騒動を教訓として、1921年に「米穀法」を制定し、政府による米価の安定と流通管理が制度化されることになります。このように、米騒動は社会政策の転換点にもなりました。
現代への教訓

米騒動は単なる「お米の値上げ」に対する怒りではなく、民衆が声を上げ、社会を動かした画期的な出来事です。そこには、
・生活に対する切実な不安
・格差や不公正への反発
・民衆による自己主張の萌芽
といった多くの要素が含まれており、現在の社会運動やデモ、インフレーションに対する不安などと通じる部分もあります。
現代日本でも
物価高騰や格差の拡大が社会問題となっています。SNSを通じて声を上げる時代ではありますが、国家や企業が生活者目線で政策や経済運営を行わなければ、再び「声なき怒り」が爆発する可能性も否定できません。

米騒動は、1918年に日本全国で発生した「米の高騰に対する庶民の怒りの爆発」であり、単なる暴動ではなく、社会構造の歪みや格差、民意の無視が引き起こした歴史的な事件でした。国家を揺るがすほどの影響を与えたこの騒動からは、今を生きる私たちにも多くの教訓が残されています
