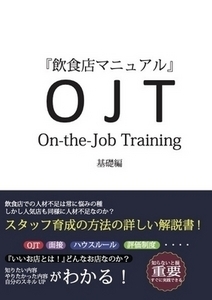スーパーで手頃な値段で購入ができ、色も鮮やかでつい手に取ってしまいたくなる夏野菜、パプリカ。生でも加熱してもおいしく、なにかと便利な野菜ですが、「パプリカにはどんな栄養素が含まれているの?」「ピーマンと似ているけど、違いは何?」など、詳しく知っている人は案外少ないのではないでしょうか。

- ピーマンも成熟すると色が変わる! ピーマンとパプリカの違い
- ピーマンとパプリカの特徴
- ピーマンとパプリカの生産地や日本での歴史の違いは?
- ピーマンとパプリカの色や大きさ、味の違いは?
- パプリカとピーマン、栄養価の違いは?
- ビタミンやカロテンが豊富な、カラーピーマンの一種
- ピーマンとパプリカのおもな特徴は?
- 生食でも、加熱してもおいしい!パプリカの食べ方
- ピーマンやパプリカの調理法の違い
ピーマンも成熟すると色が変わる! ピーマンとパプリカの違い

見た目が似ている「ピーマン」と「パプリカ」。
植物としての分類に違いはあるのでしょうか?
実は「ピーマン」も「パプリカ」も、ナス科のトウガラシ属の植物で、辛みのないトウガラシの一種になります。
「ピーマン」と「パプリカ」は同じ種ですが、栽培品種が異なります。一般的な「ピーマン」は成熟前に収穫するので緑色をしていますが、その時期で収穫せず熟させると、黄色やオレンジ、赤色へと変化していきます。これを「カラーピーマン」と呼びんでいます。
「カラーピーマン」は、大きく分けると「パプリカ」、「ジャンボピーマン」、「トマトピーマン」、「小型カラーピーマン」、「くさび型ピーマン」の5種類に分類されます。大型で肉厚な品種が「パプリカ」です。
ピーマンとパプリカの特徴

ピーマンとパプリカのそれぞれの特徴や、どのような経緯で日本で親しまれる野菜になったのかも合わせてご紹介します。
ピーマン
ピーマンの実はパプリカに比べると小さめで細長く、皮は薄めで濃い緑色をしています。味は、青臭さと苦味を感じられるのが特徴です。
普段よく食べられている緑色のピーマンは、未熟な状態で収穫されたもので、ピーマンは熟していく段階で、黄色や赤色に色が変化していきます。
色が変わる前は緑ピーマン、色が変わった後は黄ピーマンや赤ピーマンと呼ばれています。完熟したピーマンは赤色のピーマンになり、青臭さが軽減するため、ピーマンが苦手な方も食べやすく感じるでしょう。
ピーマンの原産地は中南米の熱帯地方です。明治時代にアメリカから日本に伝わり、日本で親しまれるようになったのは昭和30年代以降とされています。日本の主な生産地は茨城県、宮崎県、高知県などです。
ピーマンは加熱調理に適していて、揚げ物や高温調理をすることで苦味が和らぎます。ピーマンをパプリカで代用することもできますが、パプリカは甘いためピーマンの苦味を活かした料理には不向きです。
パプリカ
パプリカの実は、ピーマンに比べると大きく肉厚で甘味があり、生でもおいしく食べられるのが特徴です。
形はピーマンよりもふっくらとしています。
パプリカは完熟してから収穫され、ピーマンと同様に熟していく段階で黄色やオレンジ、赤色へと変色します。
原産地はハンガリーで、1990年代にオランダから輸入が始まったことで、日本でも親しまれるようになりました。韓国やオランダ、ニュージーランドからの輸入品もありますが、国内でも宮崎県、茨城県、熊本県などで生産されています。
パプリカもピーマンと同様に、加熱調理に適しています。また、甘味があり生のままでも食べられるため、サラダやピクルスにしてもよいでしょう。
パプリカの代用でピーマンを使用することもできますが、苦味があるため、調理や味付けを工夫して、苦味を抑えるとよいでしょう。
ピーマンとパプリカの生産地や日本での歴史の違いは?

ピーマンは昔から馴染みのある野菜ですが、パプリカは比較的最近になって、スーパーなどで見かけるようになりましたよね。ピーマンとパプリカの歴史や、生産地に違いはあるのでしょうか?
ピーマン
ピーマンはアメリカ原産の野菜。
日本には明治時代に入ってきたそうです。よく食べられるようになったのは、食卓が西洋化し始めた昭和30年代以降。日本国内でも数多く栽培されています。
主な生産地は茨城県、宮崎県、高知県など。
パプリカ
パプリカは、オランダからの生鮮品輸入が解禁された平成5年以降から日本でも普及し始めた野菜です。「パプリカ」という名前は、オランダ語でピーマンという意味だとか。
お手頃なお値段のパプリカは輸入品が多く、オランダ、韓国、ニュージーランドなどで生産されています。
国内での主な生産地は宮崎県、茨城県、熊本県など。
ピーマンとパプリカの色や大きさ、味の違いは?

次に、ピーマンとパプリカの大きさや、味の違いを見ていきましょう。
ピーマン
実が小さめで皮は薄く、濃い緑色が特徴です。パプリカに比べると細長い形をしています。
味は、青臭さと苦みがあります。苦味が少ないピーマンを選ぶには、「ヘタの形」に注目を。五角形よりも六角形になっているヘタのほうが、苦味が少ないそうです。
パプリカ
実は大きく、肉厚で甘みがあるのが特徴です。形はベル型とよばれピーマンと比べるとふっくらした形をしています。
赤、黄色、オレンジなど、お料理を彩るカラフルな色も魅力の一つですね。
選ぶ時は、色が濃くてツヤ・ハリ、重みがあるものを選びましょう。
パプリカとピーマン、栄養価の違いは?

ピーマンやパプリカは、ビタミンやカロテン、食物繊維などを豊富に含む野菜です。
さらに、パプリカは栄養面で優れており、ピーマンと比較してビタミンCもカロテンも約2倍以上です。
〇緑ピーマン生(100gあたり)ビタミンC: 76mg/βーカロテン当量: 400μg
〇赤パプリカ生(100gあたり)ビタミンC:170mg/βーカロテン当量:1100μg
(参考:レモン果汁(100gあたり)ビタミンC:50mg/βーカロテン当量:6μg)
また、ピーマンやパプリカに含まれるビタミンは、熱によって壊されにくい特徴があります。加熱しても効率よく栄養素を摂取できるのは嬉しいですね。
ビタミンやカロテンが豊富な、カラーピーマンの一種

パプリカは、ピーマンやトウガラシと同じ「ナス科トウガラシ属」に分類される野菜です。
学名も同じ「Capsicum annuum」で、分類上は同じもの。
日本では、果実色の特徴から通称カラーピーマンということもありますが、その中でも栽培難易度の観点から呼び方が分かれ、大きなベル型で果肉が7~10mmと厚く、黄色・オレンジ色・赤色のものを「パプリカ」と呼ぶことが多いようです。
緑色のピーマンは未熟の状態で収穫されますが、パプリカは完熟果実。
ピーマンには独特の青臭い香りと苦みがありますが、パプリカは黄色・オレンジ色・赤色と鮮やかで、甘みと酸味がバランス良く調和しているのが特徴です。
黄色やオレンジ色は、ゼアキサンチンというカロテノイドの一種の色素成分によるもの。赤色は、カプサンチンという色素成分によるものです。それぞれ「ビタミンエース」と呼ばれる、ビタミンA(カロテン)・C・Eを含んでいます。
意外に知られていませんが、実は、ビタミンCはパプリカから発見された成分。これによって、発見者はノーベル生理学・医学賞を受賞しています。
ピーマンとパプリカのおもな特徴は?

パプリカ
ジューシーで、甘みと、ほのかな酸味がある
ビタミンA(カロテン)、C、Eを含む
完熟果実
ベル型で、100g以上と大きめで肉厚
生のままでも、加熱してもおいしい
ピーマン
苦みがある
ビタミンC、A(カロテン)を含む
未熟果実
最近は肉薄のものが多い
青臭く、生食には向かない
生食でも、加熱してもおいしい!パプリカの食べ方

加熱して食べる場合も、調理法はさまざま。油で炒めればカロテンの吸収効率が良くなるほか、熱を加えてもビタミンが失われにくいところも、うれしいポイントです。パスタやピザにトッピングすれば鮮やかな仕上がりになり、煮込み料理に使っても煮崩れすることなく、おいしく食べられます。
パプリカの甘さをシンプルに味わいたいなら、オーブントースターで皮が真っ黒になるまで加熱して、皮をむいて食べるのがおすすめ。甘みが増して、より一層おいしく感じられるでしょう。
ピーマンやパプリカの調理法の違い

ピーマン
ビタミンCが豊富で、炒めるなど加熱調理をしてもビタミンが損なわれることが少ない野菜です。火を通す炒め物などにも最適です。
皮を剥く必要がなく、洗って中の種を取り除いたら、そのまま切って使えるのでお手軽です。時短で料理したい時などに使うのも良いですね。
パプリカ
パプリカは加熱時間が長いと栄養価が落ちてしまうので、調理の際は注意が必要です。
火を通す場合は、時間をかけずさっと揚げたり炒めたりしましょう。煮込む場合は、栄養素が溶け出しても飲むことのできる、スープやシチューがおススメです。
また、生でも美味しくサラダにも良く合います。